デザイン未経験のマネージャー向け|チームのデザイン力を高める「観察力」の育て方【実施編】
クリエイティブ統括本部 S.K

前回のコラムでは観察力を高めることの重要性について触れました。今回は具体的に当社で実施している取り組みについてご紹介させて頂きます。実施ハードルは高くありませんので、みなさんでも明日から試せる内容です。
オフィスに「アート」を飾る
■観察と批評を育む“Visual Thinking Strategy”という方法
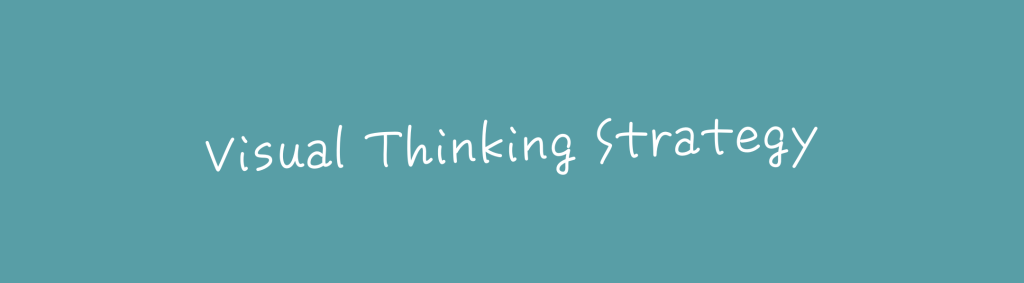
いきなりデザインではなくアートですが、アートと向き合うことも観察力と批評を育む方法のひとつです。アート鑑賞というと、どこか厳かで知識が必要そうで、なんだか手を出しづらい印象がありますよね。この取り組みを始めるまでわたしもそう思っていた一人でした。そんな中、観察力や批評を誰でも簡単に取り組める方法を探していた時に「Visual Thinking Strategy(以下VTS)」という方法と出会いました。

VTSとはアメリカ発の美術鑑賞教育法のことで、子供たちの観察力・批判的思考力・コミュニケーション力を育成する教育カリキュラムです。わたしからすると、小難しいことは置いておいて、童心の目で目の前の事象と向き合い、見えるもの、感じることを素直に言葉にすることであり、これはわたしたちデザインに携わる者が持つべき大切な姿勢のひとつだと思っています。このVTSの考え方を取り入れて、社員が日常的に、観察と批評をカジュアルに愉しめる取り組みを行うことを決めました。
※VTSについて詳しくは、こどもまなびラボ「アート鑑賞が育む3つの力」をご覧ください。
■インクルーシブアートでVTSを愉しむ

肝心なアート作品ですが、これも悩みました。当社は平均年齢が30代前半ともあり若手が多い組織です。いわゆる絵画はなんだか性に合わない・・・。いろいろと調べるうちに、とある団体のWEBサイトが目に止まりました。こちらは障がいのある方々の個性を活かし、アートを通じて社会に新しい価値を届けている団体で、その作品はどれもグラフィカルでカッコイイと感じました。グラフィックデザイナーも在籍する当社にぴったりの作品だと思い、すぐにコンタクトをとりました。こうして当社のリフレッシュスペースにアート作品が飾られる日常がスタートしました。コーヒー注ぐちょっとした間に、アートをぼんやり眺める社員もちらほらです。
※ご紹介をした団体について詳しくは、FUKU・WARAIのWebサイトをご覧ください。
■社内SNSを使ったタイトル当てクイズ
さすがデザイナーの方々で、早速興味を持って頂けました。本来のVTSであればワークショップのような場を設けて行うのですが、忙しい日々の中で時間と場所の確保はさすがに気を遣います。そこで社内SNSを使った「ゆるいアート投稿」を始めました。やり方はいたってシンプルで、タイトルを隠して「タイトルは何だと思いますか?」だけの投稿です。障がいのある方々が描く世界はとても自由で、ユニークで、意図がなかなか見えません(そこが魅力なんです)。タイトルというのは、先に聞いてしまうと先入観が生まれます。先入観に縛られると自由なアイデアは生まれづらくなります。色味、筆のタッチ、構成、謎の文字…小さな枠の中に潜むさまざまな情報を得ようと考え始めます(たぶん)。それでも分かりません。絵を投稿した日からしばらく経ってから、解答の投稿をする流れですが、楽しみにしてくれている社員も次第に増えてきました。
■ランチタイムを使ったプチ対話型鑑賞会

社内SNSだけだとやっぱり一方的なので、ランチタイムを使ってゲリラ的にプチ鑑賞会を行いました。リフレッシュスペースを利用する社員に対して、VTSの流れに沿いながらシンプルな3つの問いを繰り返す感じです。
- この作品の中で、どんな出来事が起きているでしょうか?
- 作品のどこからそう思いましたか?
- もっと発見はありますか?
時間は数分でしたが、意見を交わすことで思ってもいなかった気付きや発見があった様子です。実際にワークショップとして催す場合にはファシリテーターの腕がかなり問われます。
以上がアート鑑賞を用いた、観察力と批評を試みる当社事例でした。
外に出て観察と批評に浸る
アート鑑賞以外にも、当社ではデザイナーがチームを組んでフィールドワークを行ったりしています。実際に足を運んで、状況やターゲットを観察をして、そのデザイン(空間やコンテンツ)の意図=コンセプトを推測しあう取り組みです。この取り組みはメンバーから提案があり、ボトムアップ式で始まった活動です。意識的に取り組むことで、今後の業務にも活きる活動のひとつだと思います。
まとめ
観察だ、批評だというのは簡単ですが、社員メンバーは日々の業務に追われているので、わかっていても思考の切り替えはなかなか難しいことなのかもしれません。またマネージャーの皆さんにとっては部下やメンバーが業務以外のことに時間を使うことに抵抗がある方もいるかと思いますが、ちょっとした隙間の時間を活用したり、息抜きがてらミニイベントを催したりすることで、きっとデザインチームにとってプラスになることがあると思いますので、是非試してみて下さい。